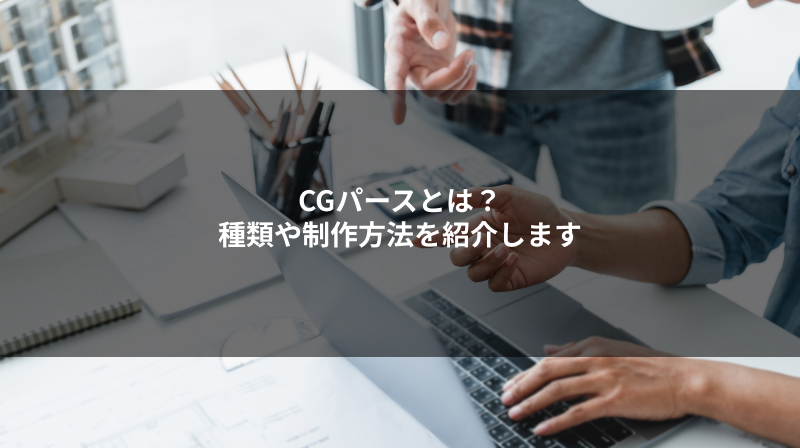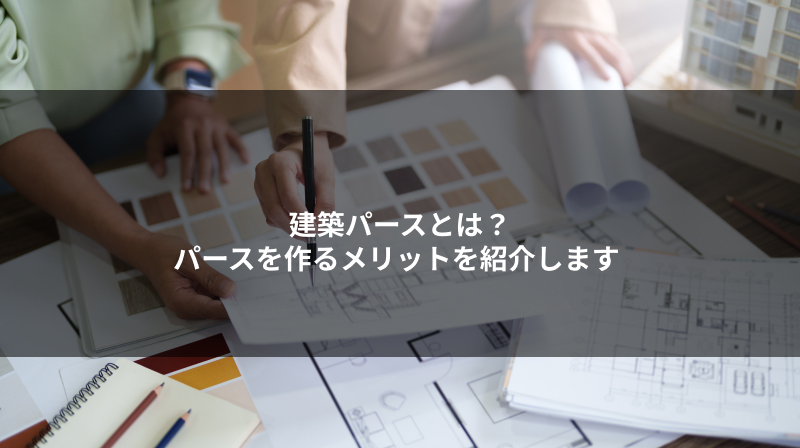こんにちは!
大阪営業所の安達です!
突然ですが谷崎潤一郎という作家をご存じでしょうか。
「細雪」や「春琴抄」「痴人の愛」などが有名ですね。
今回はそんな谷崎が日本の美について記した随筆「陰影礼賛」についてご紹介いたします。
私たちの生活空間は”明るく・清潔・機能的”これらを意識して作られることがほとんどではないでしょうか。
しかし、古来の日本建築には、真逆とも言える美の感覚が存在していました。それが「陰翳(いんえい)の美」です。
陰影礼讃では光と影の関係性こそが美を生むという、日本独特の感性が記されています。
第一に、西洋建築は、太陽の光をいかに多く室内に取り込むか、という点に重きが置かれています。高い天井、大きな窓、真っ白な壁。これらは、「影を消す」ための技術です。
一方で、日本建築では、庇は深く、障子越しに入ってくる光はやわらかく、部屋の隅にはあえて光が届かない空間が残されています。
谷崎はこう記します。
「屋根という傘を拡げて大地に一廓の日かげを落し、その薄暗い陰翳の中に家造りをする」
日本人は光を取り入れるのではなく、光を抑え、影を演出することで空間に美を宿すのです。
また、日本家屋の床の間に飾られた掛け軸や花器は、明るく照らされることを前提にしていません。ほの暗い中で、漆器の艶や金箔の反射がわずかな光に応じて静かに輝く。これこそが「陰翳の美」の真髄です。
他にも、谷崎は現代の明るすぎる照明についてこうも記しています。
「今日の室内の照明は、書を読むとか、字を書くとか、針を運ぶとか云うことは最早問題でなく、専ら四隅の蔭を消すことに費やされるようになった」
これは「闇=不快、不便」とする西洋的価値観が日本にも入り込み、私たちが本来持っていた「暗がりの美」を失いつつあることへの警鐘でもあります。
最後に陰影礼賛の中でもとくに有名な科白を紹介します。
「日本家屋というものは、どこかに闇を残しておきたいという気持から出来ている。われわれは光線を殺して、陰翳の中に落ちつきを感じ、閑寂を楽しむ。」
「西洋人はどこまでも明るくしようとするが、われわれはわざと光を抑え、闇をつくって、その中に美を見出した。」
日本人は明暗の境界がぼんやりと溶け合う空間、“完全ではない美”に心の安らぎを感じてきたのかもしれませんね。
そんな「谷崎的日本の美」、オフィス設計をされる際にも是非取り入れてみてはいかがでしょうか~。
■この記事もおすすめ
業界に精通したプロが解説!オフィス移転でやることチェックリスト17!
オフィスでできる感染対策7選!3つの密を避けるコツとは?
オフィスのおすすめレイアウトをご紹介!仕事の効率が上がる配置とは?
【就活生の企業選びの基準と採用に向けた企業側の対策】 就活生の8割以上の方が企業選びにおいてオフィス環境を重要視!