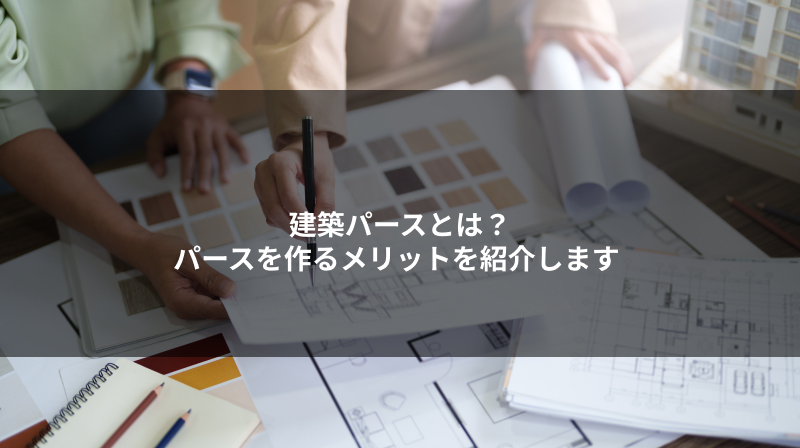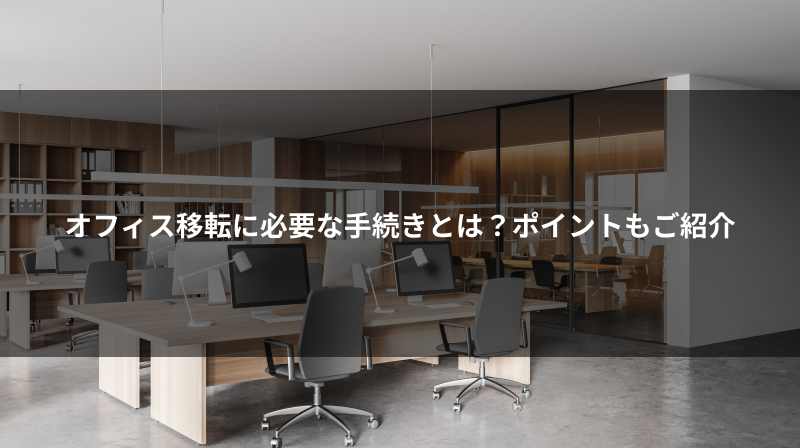
オフィス移転の手続きは、企業の成長や事業拡大に伴って避けては通れない業務の一つです。
しかし、オフィス移転には多くの法的・実務的な手続きがあり、担当者が初めての場合には「何から始めれば良いかわからない」と感じることもあるでしょう。
最近では、働き方の多様化やリモートワークの普及により、オフィスの在り方自体を見直す企業も増加傾向にあります。
その結果、「移転先の選定」だけでなく、「手続きやスケジュール管理」までを効率的に行う重要性が高まっています。
そこでこの記事では、中小企業の企画部門向けに、オフィス移転に必要な手続きと、その進め方のポイントをわかりやすくご紹介いたします。
目次
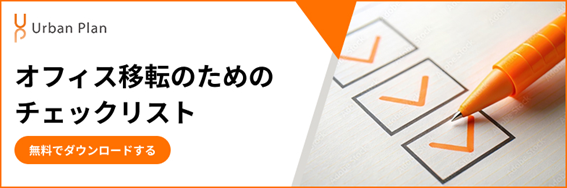
オフィス移転に必要な手続き①各種ライフライン・サービスの手続き
オフィス移転の際に最初に着手すべきなのが、各種ライフラインや通信インフラに関する手続きです。
これら手続きが遅れると、業務再開の遅延や社内外の混乱を招く恐れがあるため、計画的かつ早期に対応する必要があります。
インターネット・電話・電気・ガスの手配と変更
移転先でもすぐに業務を開始できるよう、インターネット回線や電話、電気・ガスといった基幹インフラの手続きは最低でも1ヵ月前には進めておく必要があります。
インターネット・電話回線
現在の契約業者に移転手続きの可否を確認し、移転先での工事日程を調整します。
オフィスビルによっては特定のプロバイダしか対応していないケースもあるため、早期の確認が重要です。
電気・ガス
エリアによって管轄が異なるため、新住所が管轄となる電力・ガス会社への開通依頼を行いましょう。
また、使用開始日に立ち会いが必要な場合もあるため、スケジュール管理も重要です。
特にインターネット回線は、申し込みから開通までに時間がかかるケースが多く、業務に支障が出ないよう予備回線やモバイルWi-Fiの一時導入も検討すると安心です。
郵便物の転送・住所変更
郵便物の転送手続きも忘れてはならない項目です。
日本郵便では「転居・転送サービス」を提供しており、事前に申し込むことで旧住所宛の郵便物を1年間新住所に無料で転送してくれます。
これに加え、名刺やパンフレット、会社ホームページなどに記載されている住所表記も同時に見直しを行いましょう。
情報の更新もれは信頼性の低下につながるため、チェックリスト形式で管理するのがおすすめです。
チェックリストは、このページの下部をご覧ください。
オフィス家具・什器の搬出入手配
オフィス家具や什器の搬出・搬入も、移転業務の大きなウェイトを占めます。
搬出は現オフィスの退去期限に合わせ、搬入は新オフィスのレイアウト工事の完了後に実施するのが理想的です。
移転スケジュールに合わせて搬出・搬入が可能な業者を手配しましょう。
オフィス移転は、新しいスペースやデザインに応じて家具の再配置や新規購入を検討するタイミングでもあります。
専門業者によるレイアウト設計や内装工事のトータルサポートを受けることで、作業効率やコストパフォーマンスを高めることができるでしょう。
オフィス移転に必要な手続き②法的・行政的な届け出関係
オフィスを移転する際には、住所変更に伴う各種届け出が必須です。
主に「法人登記」「税務」「社会保険」「労働関連」に分かれており、それぞれの手続きを正しく行わなければ、法的リスクや行政手続きの遅延を招く恐れがあります。
計画段階からもれがないようリストアップし、順序立てて進めることが重要です。
法務局
法人の所在地が変更になる場合は、法務局での「本店移転登記」が必要です。
登記は移転日から2週間以内に完了させる義務があり、これを怠ると「登記懈怠」とみなされ、過料の対象になる可能性もあるため、注意が必要です。
登記に必要な書類は、本店移転登記申請書、取締役会議事録、株主総会議事録(必要な場合)などです。
事前に司法書士や税理士、社会保険労務士などの専門家に確認することをおすすめします。
税務署・都道府県税事務所
移転に伴い、税務署や都道府県税事務所へ「異動事項に関する届出」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出します。
これは本社所在地の変更により納税地が変わることを知らせるためのもので、移転後すぐの提出が求められます。
社会保険事務所・年金事務所
移転に伴い、これまでの年金事務所が管轄する地域外へ所在地変更する場合は、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出する必要があります。
労働基準監督署・ハローワーク
労働基準監督署には、「労働保険 名称、所在地等変更届」の届出が求められます。
また、ハローワークへは、「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出し、従業員の雇用保険情報を正確に反映させる必要があります。
ハローワークでは、労働基準監督署に提出した「労働保険 名称、所在地等変更届」の控が必要なため、順番としては、労働基準監督署の後、ハローワークへ行きましょう。
オフィス移転に必要な手続き③取引先・関係者への連絡と広報対応
オフィス移転が社内の準備だけで完結すると思っていると、大きな落とし穴にはまる可能性があります。
取引先や顧客、協力会社、業務委託先など、関係各所への「移転の連絡」がもれると、信用問題やトラブルにつながりかねません。
外部への通知も計画的に進めましょう。
取引先・顧客へのお知らせ文の作成と送信
まずは、取引先・顧客など外部に向けたオフィス移転のお知らせ文(通知書)の作成に取り組みましょう。
さらに、宛先リストを整備し、送付もれがないように管理します。
通知の方法は以下のように複数、考えられます。
・郵送による案内文送付
・メールによる一斉送信
・FAXによる案内(高齢層の多い業界など)
・直接訪問による挨拶(重要顧客の場合)
通知書には、新住所・電話番号・アクセス方法・移転日・業務開始日・問い合わせ先などの情報を明記し、受け手が混乱しないよう配慮しましょう。
営業担当が直接フォローすることで、関係維持にもつながります。
公式Webサイトや名刺・パンフレットの更新
企業の「顔」ともいえる公式Webサイトの情報更新は、移転日の前後で最優先事項です。
住所変更が遅れると、訪問者や応募者、取材依頼などにも悪影響が及ぶ可能性があるためです。
特に以下の情報更新を忘れずに行いましょう。
・サイトの会社概要ページの住所・地図・連絡先、アクセス案内ページ
・フッター表記の会社情報
・採用ページ
移転のニュースをプレスリリースやSNSで発信することもおすすめです。
オフィスの移転は、自社の成長や新たなステージへの「象徴的な出来事」として、社外へのポジティブなメッセージにつながります。
さらに、名刺や会社パンフレットなどの紙媒体も再印刷が必要です。
部署ごとの更新もれや旧データの誤使用を防ぐため、社内で一括管理をするのが理想的です。
印刷に時間がかかる場合は、一時的に印刷用シールで対応する方法も検討できます。
また、移転の機会に合わせて、リブランディングを行い、ロゴやデザインを刷新する企業もあります。
オフィス移転を成功させるチェックリスト
オフィス移転では、事前にチェックリストを作成しておくことで、抜けもれを防ぎ、移転作業をスムーズに進めることができます。
事前準備フェーズ(3~6ヵ月前)
□移転理由・目的の明確化(契約満了、拡張、コスト削減など)
□経営陣からの正式な承認取得
□新オフィス候補地の選定・内見・比較
□賃貸契約交渉・契約締結
□現在のオフィスの解約通知・原状回復条件の確認
□オフィス移転スケジュールの作成と社内共有
□プロジェクトチーム・担当者の任命と役割分担
移転計画フェーズ(2~3ヵ月前)
□引越し業者の選定と見積もり取得
□レイアウト設計・内装工事の打ち合わせとスケジューリング
□ITインフラ設計・通信設備の構築計画立案
□家具・什器・備品の選定・購入
□業者・ベンダーとの調整(プロバイダー、印刷会社など)
□移転に伴う法的手続き・行政手続きの一覧化
□移転のお知らせ文テンプレートの準備
実行フェーズ(1ヵ月前~当日)
□各種届出の提出(法務局、税務署、社会保険事務所など)
□取引先・顧客への案内状送付・メール配信
□郵便転送手続き
□名刺、パンフレット、Webサイトの情報更新
□荷物の梱包と廃棄物の処分(不要什器の整理)
□新オフィスの最終確認(電気・通信の動作チェック)
□引っ越し実施(スムーズな搬出入の管理)
移転後
□社内へのリマインド通知とオリエンテーション実施
□新オフィスの防災・セキュリティ対策の再確認
□社員の意見収集(改善点や課題抽出)
□取引先からの反応・連絡先変更漏れの確認
□内装やレイアウトの追加調整(必要に応じて)
まとめ
オフィス移転は、単なる引越しではなく、企業運営に関わる多面的な手続きを含むプロジェクトです。
インフラ整備や行政手続き、取引先への通知、社内広報まで、段取り良く対応することが重要です。
チェックリストを活用し、社内の連携を取りながら確実に進めていきましょう。
もし、レイアウト設計や内装工事、工程管理をプロに任せたいとお考えの場合は、アーバンプランのオフィス移転サービスの活用もご検討ください。計画から実行までトータルで支援いたします。